この記事では、水質関係公害防止管理者の水質有害物質特論に合格することを目標として、各科目の勉強をしていきます。
前回は「有機りん・PCB排水の処理」を解説しました!
今回は「有機塩素化合物・農薬系有機化合物排水の処理」について勉強していきます。
【有機塩素化合物排水の化学的性質】
有機塩素化合物は以下の物質です。
いずれも、水に溶けにくく(疎水性)、アルコール、エーテル、ベンゼンにはよく溶けます。
水よりも重いので、水と混合したものを静置すると2層に分離し、下層に沈む。
【有機塩素化合物物排水の処理方法】
有機塩素化合物排水の処理方法としては、
があります。
それでは、詳しく見ていきましょう。
①活性炭吸着法
有機塩素化合物は疎水性なので、活性炭で吸着ができます。しかし、吸着量が少なく、排水の濃度が低くなるほど、活性炭の単位質量あたりの吸着量が減少し、処理効率が悪くなる。
また、他の有機物が共存している場合も吸着量は減少します。
②酸化分解法
有機塩素化合物は、酸化剤で二酸化炭素と塩化物イオンに分解することができます。
中性から酸性の領域でよく分解され、酸化剤は過マンガン酸塩やオゾンなどがあります。
③揮散法
排水に微量に溶解している有機塩素化合物は、空気を吹き込み曝気すると、大気中に揮散し、除去できます。揮散した有機塩素化合物は、活性炭塔を通して吸着除去するか燃焼して処理します。
④生物処理法
有機塩素化合物を分解できる微生物は
の特殊な細菌に限られる。
通常、有機塩素化合物を含む排水には、他に生物酸化されやすい有機物も多量に含まれていることから、活性汚泥で処理した場合はこれらの有機物を分解する細菌の方が優勢に働いて、メタン資化菌は共生しにくい。
しかし、有機塩素化合物で汚染された土壌、地下水の浄化方法としてバイオレディメーションが注目されています。
バイオレディメーションには以下の2通りがあります。
バイオオーグメンテーション
塩素化エチレン分解菌を培養した液を汚染土壌、地下水に直接注入して有機塩素化合物を分解する方法です。
バイオスティミュレーション
汚染土壌、地下水に栄養物質を注入し、有機塩素化合物を分解できる細菌を活性化して分解する方法です。
バイオレディメーションの内容は試験に出題されやすいのでよく覚えておきましょう。
【農薬系有機化合物排水の化学的性質】
農薬系有機化合物には以下の物質があります。
【農薬系有機化合物排水の処理方法】
農薬系有機化合物の処理方法には
があります。
特徴を見ておきましょう。
①活性炭吸着法
農薬系有機化合物は疎水性であるため、活性炭吸着法は適用されます。
吸着量は小さいが、有効な処理法です。
②逆浸透膜
農薬系有機化合物は分子量が大きいので、逆浸透膜による処理が可能です。
しかし、膜の洗浄廃液や濃縮水の処理が課題となります。
まとめ 水質有害物質特論「有機塩素化合物・農薬系有機化合物排水の処理」の勉強
有機塩素化合物では活性炭吸着法、酸化分解法、揮散法、生物処理が可能です。
特に生物処理のバイオレディメーションはバイオオーグメンテーションとバイオスティミュレーションの2通りあります。
塩素化エチレン分解菌を直接注入するのがバイオオーグメンテーション、栄養物質を用いて塩素化エチレン分解菌を活性化し処理するのがバイオスティミュレーションです。
農薬系有機化合物は活性炭吸着法と逆浸透膜で処理できます。特に、逆浸透膜で処理できることは試験に出やすいので、注意しましょう。
水質関係公害防止管理者試験の水質有害物質特論は難関科目ですが、一つずつ勉強していきましょう。


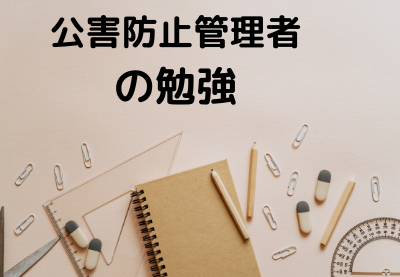














0 件のコメント:
コメントを投稿