この記事では私が「大気関係第一種公害防止管理者」と「水質関係第三種公害防止管理者」の資格をとって得た「メリット」と取得するまでにした「勉強方法」について解説します。
公害防止管理者ってなに
公害防止管理者は以下の業種の工場(特定工場)において選任しなくていけない必置資格です。
義務づけられている業種では、公害防止組織をつくり、公害防止管理者を選任しなくてはなりません。
この4つの業種はすべての業種で選任しないといけないわけではなく、
常時使用している従業員数が21人以上でかつ、排気量、排水量が一定量以上の工場でのみ選任が必要となってきます。
公害防止管理者には多くの資格区分があり、その中でも特にメジャーなのが、
大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者です。
試験は年一回で、毎年7月から願書受付が開始され、試験日は10月の第一日曜日に実施されます。
合格率は約20%前後とされていいますが、科目合格があるので、一回で合格する必要はなく、3年かけて取得すればOKです。
(3年経つと科目合格がなくなってしまうので、再度受けなおさなければいけません)
公害防止管理者取得の経緯
私の勤めている工場では、実は公害防止管理者の選任は必要ありません。
排気量、排水量が低いので、公害防止管理者の選任は必要なくとも、常時使用している従業員数が300人程いるので、形だけでも公害防止組織をつくることとなったので、公害防止管理者の資格が必要となりました。
私が資格を取得するまでは、外部の分析会社に委託して、公害防止組織を作っていました。
そこで、私が資格を取るように会社から言われ公害防止管理者を受験することとなったのです。
まず、私が合格を目指したのは「大気関係第一種公害防止管理者」でしたが、大気関係第一種公害防止管理者に合格するまでには、
の6科目を合格しなくてならなく、一気にすべてを合格する自信もなく、科目合格も3年でリセットされてしまうので、
とりあえず、「大気関係第三種公害防止管理者」から受験をすることとしました。
大気関係第三種公害防止管理者の受験1回目(不合格)
初年度は初受験のため、
・公害総論
・大気概論
・大気特論
・ばいじん・粉じん特論
・大規模大気特論
の5科目を受験しました。
そのうち、
「公害総論」と「大規模大気特論」の2科目が合格で
「大気概論」、「大気特論」、「ばいじん・粉じん特論」の3科目は不合格でした。
初年度は
の2冊で勉強をしました。
超速マスターでポイントを読んで、過去問である攻略問題集を解くといった勉強をしていたのですが、
初年度は完璧に完ぺきに勉強不足でした。
勉強時間としたら、3か月程で、平日は通勤時間の往復で本を読んだり、休みの日に攻略問題集を解いたりしていた程度で、合計でいったら30時間程だったと思います。
公害総論は自信があったのですが、正直、合格した大規模大気特論はラッキー要素が強いです。
大気関係第三種公害防止管理者の受験2回目(合格)
初年度で失敗した経験を踏まえ、2年目は真剣に勉強をしました。
使用した参考書は初年度と同じく、
の2冊で勉強をしました。
公害防止管理者を受験するときの参考書で有名な「新・公害防止の技術と法規」は購入しませんでした。
価格が非常に高いというのもありますが、私が勉強するのは「会社のすきま時間」や「通勤電車」の中が多いので、重すぎて持ち運びに不便という理由が大きいです。
超速マスターの方は、必要な内容が整理されていて、コンパクトなので電車の中でも読みやすいので重宝しました。
攻略問題集の方は、基本的に過去問なので、各科目2周程解きましたが、
ネットに平成18年からの過去問が記載されているホームページを見つけたので、そこで会社の昼休憩中にひたすら過去問を解いていました。
勉強時間はやはり3か月程で、
トータルの勉強時間は大気概論、大気特論、ばいじん・粉じん特論の3科目で60時間勉強しました。
1回目の受験と合わせると90時間となります。
結果は3科目とも合格で、
大気関係第三種公害防止管理者合格となりました。
合格に一番役立ったのが、「最短合格公害防止管理者大気関係超速マスター」でした。
購入するときのレビューとしては賛否両論といった感じでしたが、
内容はきちんとまとめられていますし、なにより要点だけまとめられているので、試験の直前もこれを読んでいました。
正直、公害防止管理者の勉強内容はボリュームが多すぎてすべてを勉強しようとするとものすごく時間がかかります。
最初に「新・公害防止の技術と法規」で勉強を始めると、挫折してしまう人が多いです。
というより、会社の後輩なんかはこの「新・公害防止の技術と法規」を見ただけで挫折して、受験をあきらめていました。
(会社には昔の本が何冊かありました)
後は、過去問から類似問題が多く出題されるので、過去問はすべての年代で100点をとれるまでやりました。
大気関係第一種公害防止管理者の受験(合格)
第三種公害防止管理者を受験した翌年に大気関係第一種公害防止管理者の受験をしました。
第三種公害防止管理者を合格していたので「大気有害物質特論」のみの受験となりました。
この科目は、暗記する量がかなり多かったので
を購入して勉強をしました。
「受験科目別問題集」は試験を実施している社団法人 産業環境管理協会が出版しているだけあった非常に分かりやすかったです。
単元毎にきちんと解説もあり、問題も過去問から出されているので、こちらで勉強するのであれば、超速マスターの方は必要なかったとも感じました。
ただ、単元ごとになるので、多くの科目を受験する場合、すべてそろえるとなると結構お金がかかってしまいます。
この受験科目別問題集で勉強して、また会社の昼休憩に過去問を解いて、勉強時間としては、
1科目だけっていうのもあり、2か月で30時間程、結果は合格でした。
大気関係公害防止管理者を取得したメリット
大気関係公害防止管理者を取得して得たメリットとしたら、公害防止管理者に任命されたので会社から、毎月4000円の資格手当がつくことになりました。
同じく持っている甲種危険物取扱者は資格手当が500円なので、努力したかいがありました。
私は、大学は化学科(学部卒)でしたので、甲種危険物から公害防止管理者と資格を取得していくというオーソドックスな流れでした。
このままの勢いで次はエネルギー管理士を取得しようとも考えていました。
エネルギー管理士の熱分野とはかぶっている内容があるので、このままの勢いで勉強していけばいけるのではと思い勉強していっていました。
しかし、ある日会社から次は水質関係公害防止管理者も取得するように言われてしまいました。
水質関係第三種公害防止管理者の受験(合格)
水質関係第一種公害防止管理者は
の5科目の受験科目があります。
会社から水質関係公害防止管理者を取得するように言われてしまったので、
勉強していたエネルギー管理はいったん保留として、
とりあえずまたもや、一発で一種に合格する自信はないので、
水質関係第三種公害防止管理者の受験を決めました。
第三種になると「水質有害物質特論」がなく
私は、大気関係公害防止管理者を取得しているので
「公害総論」も免除されるので
実質3科目だけの受験となりました。
使用した参考書は
を購入しました。
3科目だけというので、少し余裕を感じていたのですが、
「汚水処理特論」のボリュームにビビッてしまい、慌てて科目別問題集を購入しました。
この科目は「科目別問題集」を購入してよかったと思いました。
出題範囲が広いので超速マスターのみではカバーできなかったと思います。
あとの2科目は超速マスターと過去問を解いていて問題はなかったです。
基本的に超速マスターを使って、用語の学習、会社の昼休みに過去問を延々と説くを繰り返し、トータルの勉強時間としては80時間程で合格することができました。
(コロナ過で一度受験を見送りました)
現在、最後の「有害物質特論」を勉強しているところです。
まとめ
公害防止管理者を勉強して得たメリットとしては資格手当が4000円でした。
大気関係公害防止管理者とエネルギー管理の熱分野では内容が被っている部分があるので、続いて勉強すると有利です。
勉強する内容としては、出題範囲が非常に広い為、空いている時間でちょこちょこと読める本がおススメです。
過去問をできるだけ解いて、すべての年で100点をとれるようになれば、十分合格できる実力はつきます。
もちろん、「新・公害防止の技術と法規」で勉強をするとより確実になると思います。
モチベーションがつづくのであれば購入を検討してもよいでしょう。
とりあえず、私は水質関係第一種公害防止管理者を目指して、残りの「水質有害物質特論」の勉強をしていきます。


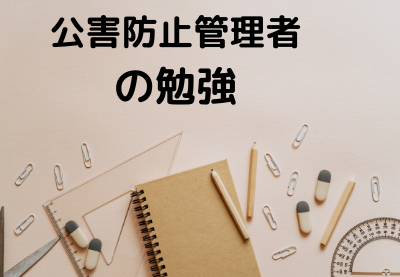
















0 件のコメント:
コメントを投稿